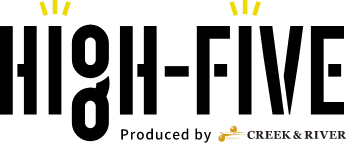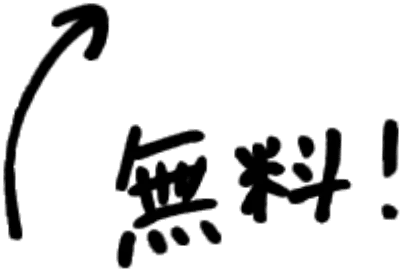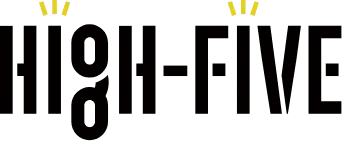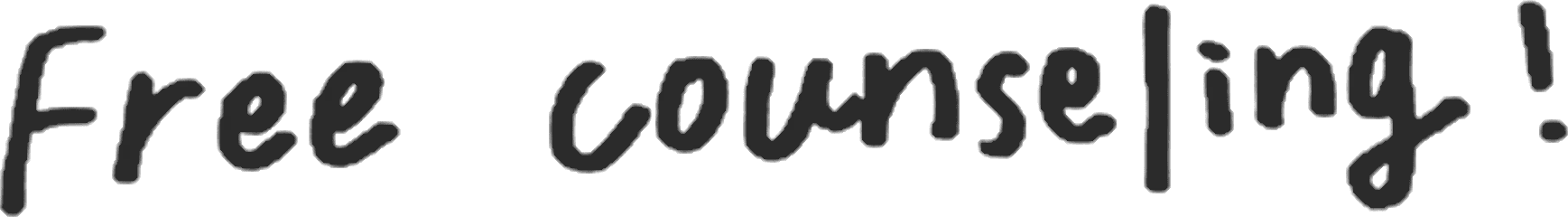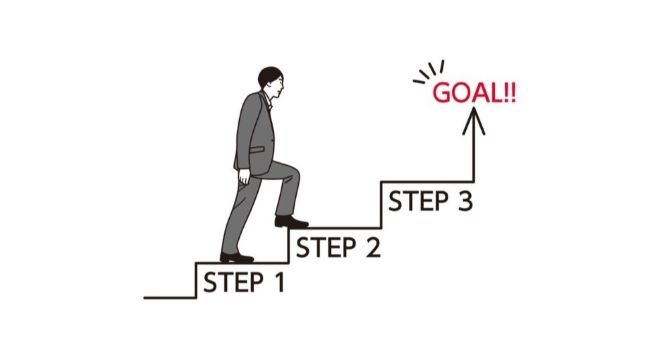転職時にWebデザイナーが『評価される』ポートフォリオの作成ポイント|Webデザイナー・クリエイター専門の転職エージェントHIGH-FIVE
公開日:2022/12/21
変更日:2025/07/08

\ポートフォリオの詳しい作り方を教えます!/
クリエイターの転職活動に必ずついて回るのが「ポートフォリオ」。特にデザイナーにとって、自分の持っているスキルや今までの実績をわかりやすく伝えるための重要な資料です。
ところで。
あなたのそのポートフォリオ、本当にわかりやすいですか……?
そもそも採用担当にとっての「わかりやすい」とはなんぞや……
もし、自分の魅力が確実にわかりやすく伝わりそうなポートフォリオを作ることができたら、より自信をもって転職活動できそうですよね!
そこで今回は、クリエイターの採用において実際に採用担当が見ているポイントおよびそれに沿った評価されるポートフォリオの作り方をHIGH-FIVE転職エージェントの川原に教えてもらいました。ポートフォリオに載せてはいけないものなど、良くいただく質問にも答えていますので、ぜひ参考にしてみてください!
目次
デザイナーの転職でポートフォリオが必要な理由
こんにちは、HIGH-FIVE転職エージェントの川原です。
まず、ポートフォリオを作成するにあたってなぜデザイナーの転職には「ポートフォリオ」が必要なのかということをおさえておきましょう。
まずポートフォリオは、過去のプロジェクトやデザインの実績を具体的に示すためのツールです。デザイナーが持つ多様なスキル(グラフィックデザイン、UI/UXデザイン、イラストレーションなど)を示すことで、幅広い能力をアピールできます。同時にデザインのアイデアがどのように生まれ、どのように具体化されたかを説明することで、デザイン思考やプロセスを理解してもらえるでしょう。
また言葉だけでなくビジュアルで示すことで、応募先企業のブランドやスタイルにどれだけ適合するデザインができるかをアピールできます。自分のデザインスタイルや個性を表現する場でもあるのでポートフォリオによって、他の応募者との差別化を図ることもできます。
このようにポートフォリオは、デザイナーのスキル、経験、創造性、問題解決能力、個性を具体的かつ視覚的に示す重要なツールであり、デザイナーの転職活動において不可欠な要素となっているのです。
ポートフォリオに必要な5つの項目
プロフィール
名前や連絡先などの基本情報はもちろん、自己紹介やキャリアの要約を記載します。自分がどのようなデザイナーで、何に興味があるのかを簡潔に伝えましょう。
スキルレベル
自分のスキルを明確に示すために、使用できるデザインツール(Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Sketch、Figmaなど)と使用年数、その他具体スキル(UIデザイン/UXデザイン/グラフィックデザイン/プロトタイピング/モバイルデザイン/フロントエンド技術などあれば)を記載しましょう。
関連する学歴や資格などもあれば記載しておきましょう。
過去の作品・成果物
自分が担当した成果物のスクリーンショットや、オンライン上で閲覧可能なものはリンクURLを記載しましょう。その際、作品ごとに「プロジェクト名とその説明」「使用ツール」「担当した役割と貢献度」「成果・反響」は必ず記載するようにしましょう。実際のクライアントやチームメンバーからのコメントなどもあると信頼性が向上します。
得意なデザインと業務で心がけていること
「カラフルでポップなトーン」「女性向け商材」など得意とするジャンル・デザインや、業務プロセスにおいて重きをおいているポイント(例:UX、ペルソナ作成、クライアントとのコミュニケーション等)を記載しましょう。
将来のビジョン
この先どのようなデザイナーになりたいか、それに向けてどのようなスキルや経験を積みたいかを具体的に述べましょう。自分自身のスキル向上だけでなく、チームや事業ひいては社会にどう貢献したいかが添えてあると尚良いです。
採用担当者がポートフォリオを見るときのポイント
次に、採用担当者が見ているポイントを整理します。
 成果物およびポートフォリオのデザイン品質
成果物およびポートフォリオのデザイン品質
成果物のデザインはもちろん、ポートフォリオそのもののデザインについても見られていると考えましょう。適切なセクションにわかりやすく整理され、視覚的に洗練されているかどうか意識しましょう。
スキルレベルや使用できるツール
成果物のデザインと併せ、求人票に記載されている要件と一致しているかどうかチェックされています。
デザインへのこだわりや創意工夫
成果物ごとに、どのようなオーダーに対し、どのように取り組み、解決した結果なのかを見られています。説明文の内容から、コミュニケーション能力についても見ている場合があります。
評価されるポートフォリオにするための4つのポイント
全ての基本は「読み手の立場を考える」こと
書類選考の過程で関わってくるのは主に人事担当者と現場担当者ですが、人事担当者はあくまで窓口であり、実際にポートフォリオを詳しく見るのは現場担当者です。それを踏まえて、まず避けておきたいのが以下の2点です。
・容量が重たすぎるもの
・データ以外の提出方法(紙やファイルの郵送)
現場担当者は、本業と並行しながら空いた時間に応募書類を見ています。たとえ本業の手が空いていたとしても、まず書類のダウンロードに5分、開くのに5分……というのは煩わしく感じてしまいますよね。直接合否に関わるポイントではないものの、読み手の立場を考える意識は持っておきましょう。
また最近はほぼないとは思いますが、郵送でいきなり送り付けるのもNGです。企業側が指定した形式で提出するようにしましょう。なお、面接で印刷したものを見せながらお話するのはOKです。
ポートフォリオ自体も「作品」と意識する
書式についても、読み手を意識しながら作ることが大切です。上記でも触れましたが、今まで作ってきたものを単に貼り付けるだけのポートフォリオは避けたほうが吉です。なぜなら、成果物に対してあなたがどう関わってきたのかがわかりづらいからです。
映像のクリエイターも、自分のポートフォリオをテンポよく見てもらうために、複数の映像を1つの作品として編集しまとめます。Webであってもポートフォリオは1つの作品として意識し、起承転結でまとめると良いでしょう。
ポートフォリオ作成が上手な方は、ご自身のキャリアに沿って流れを構成している方が多いです。例えばWebデザイナーであれば、成果物を時系列に並べつつ、「青のアイコンは制作会社時代」「赤のアイコンは事業会社時代」と色分けするなどですね。
さらに、デザインに対してあなたは何の役割を担ったのかもテキストで記載するようにしましょう。一言にデザイン担当といっても、例えばコーディングまで担当したのか、ワイヤーだけつくって外部業者にアウトソースしディレクションをしたのか。制作期間はどれくらいで、なぜこのようなデザインにしたのか。などが自分の言葉で書かれていると、その人の具体的な仕事ぶりが想像しやすくなります。
成果物を提出した「その先」まで伝えよう
 また忘れずに必ず記載してほしいのは、このデザインをした「結果」です。Before/Afterの形で書かれているとよりわかりやすいです。売上が伸びた・滞在時間が伸びた・アクセスや資料請求が増えたなど、特に事業会社に行きたい場合は必須と思っていただいたほうが良いです。
また忘れずに必ず記載してほしいのは、このデザインをした「結果」です。Before/Afterの形で書かれているとよりわかりやすいです。売上が伸びた・滞在時間が伸びた・アクセスや資料請求が増えたなど、特に事業会社に行きたい場合は必須と思っていただいたほうが良いです。
もし受託のお仕事で詳細な結果数値までは開示されなかったとしても、わかる範囲で良いのでできるだけ記載しましょう。「受託のためエンドユーザーの話までは聞けていませんが、先方担当者に〇〇の点で評価いただきました」と書いてあるだけでも、デザイン完成のその先まで意識していることが伝わりますよね。
なお、当たり前のことではありますが、情報解禁前の成果物を許可なくポートフォリオに載せることは絶対にNGです。もちろん、ボツ案の掲載であってもNGです。
どうしてもメインでアピールしたいご経験が解禁前の成果物にひもづく場合は、我々転職エージェントにご相談ください。伝え方のアドバイスもできますし、詳細を伏せつつ応募先企業に推薦することも可能です。こういったご相談はもちろん無料ですので、うまく使ってほしいと思います。
ほんの少しの工夫で差がつけられる
我々転職エージェントは、デザインの詳しいノウハウやテクニックの知識などは本職のデザイナーさんたちに敵いません。ですが、クリエイター転職のプロとして「採用企業にアピールできているか否か」はわかります。
ポートフォリオは、クリエイターの転職活動において一番最初に見られる大切な書類であるにも関わらず、あまり手をかけられていない現状があると感じています。ポートフォリオでうまく魅力を伝えられていないがために、書類選考に通らない例を実際に見てきています。
多くの人が成果物をただ貼り付けて提出してしまいがちなポートフォリオだからこそ、そこに気を付けるだけでも「お!」と思ってもらいやすくなります。デザイナー・クリエイターとしての力をアピールしたいわけですから、ポートフォリオ自体もデザインするつもりで作成しましょう。
転職活動は相対評価!惜しくも”落ちる”ポートフォリオの特徴、教えます▼
Webデザイナーのポートフォリオに関してよくある質問
Q1:Webデザイナーの転職でポートフォリオは必須ですか?
Webデザイナーを目指すなら、ポートフォリオは必要不可欠でしょう。
企業はどのような作品を作れるのか、どのようなスキルを兼ね備えているのかを把握した上で合否を決めますが、その判断材料になるのがポートフォリオです。ポートフォリオを通じて、具体例を示すことで実際のスキルや創造性をアピールすることができます。また、デザインプロセスや問題解決能力、そして独自のデザインスタイルを企業に伝える手段としても非常に重要です。ポートフォリオが充実していることで、企業は志望者が会社のビジョンやプロジェクトに適合するかどうかを評価しやすくなり、採用の際の重要な要素となるのです。
Q2:ポートフォリオの作品数はいくつあると良いですか?
ポートフォリオに掲載する作品は、10~15作品を目安にしましょう。これまでの作品をできるだけ多く載せたい方もいると思いますが、応募企業に求められているデザインの方向性にあっているか、作品の羅列だけではなくしっかりと説明がされているかなどに気を付けながら、量より質を意識したポートフォリオにするよう心がけましょう。
Q3:ポートフォリオに載せてはいけないものはありますか?
ポートフォリオに載せる作品は、自分が手掛けたデザインや実績であればある程度許容されていますが、著作権や守秘義務に触れてしまうようなものは掲載してはいけません。お世話になった前職や、応募先の企業によい印象を持ってもうためにも配慮を忘れずに制作してください。
まとめ
評価されるポートフォリオ、作れそうな気がしてきましたか?これから新しく作成する方も、今まで使っていたポートフォリオを手直しする方も、ぜひ上記の視点を参考にしてみてくださいね。
ちなみにHIGH-FIVEの転職エージェントでは、転職支援の一環としてポートフォリオの添削・制作支援も行っています。本記事でもご紹介したように、各エージェントが現場の採用担当者の求めるポイントを熟知しているため、”選考を通過しやすいポートフォリオ”の制作を支援することが可能です。
もちろんご相談はすべて無料なので、プロの視点で添削してほしい!という方はぜひ気軽にご相談してみてくださいね。お待ちしています!
この記事を書いた人

HIGH-FIVE編集部

クリエイティブ業界に精通した転職エージェントが、一人ひとりの転職活動をきめ細かくフォロー。
ご登録いただくことで、あなたの強みを引き出し、企業との本質的なマッチングを叶えます。